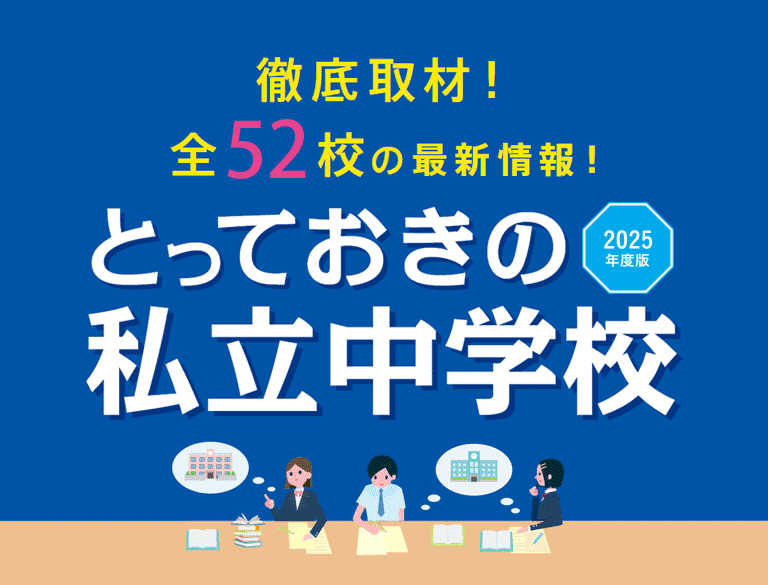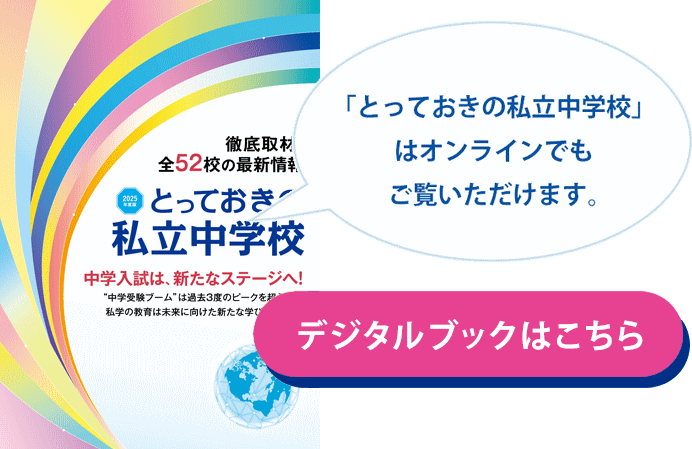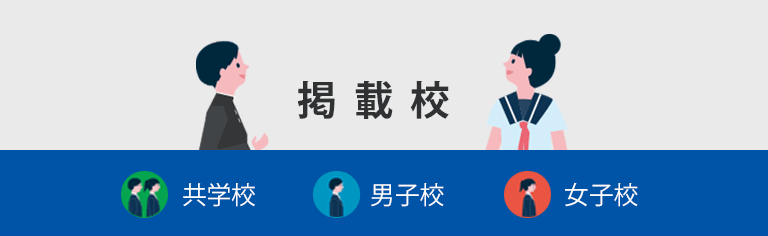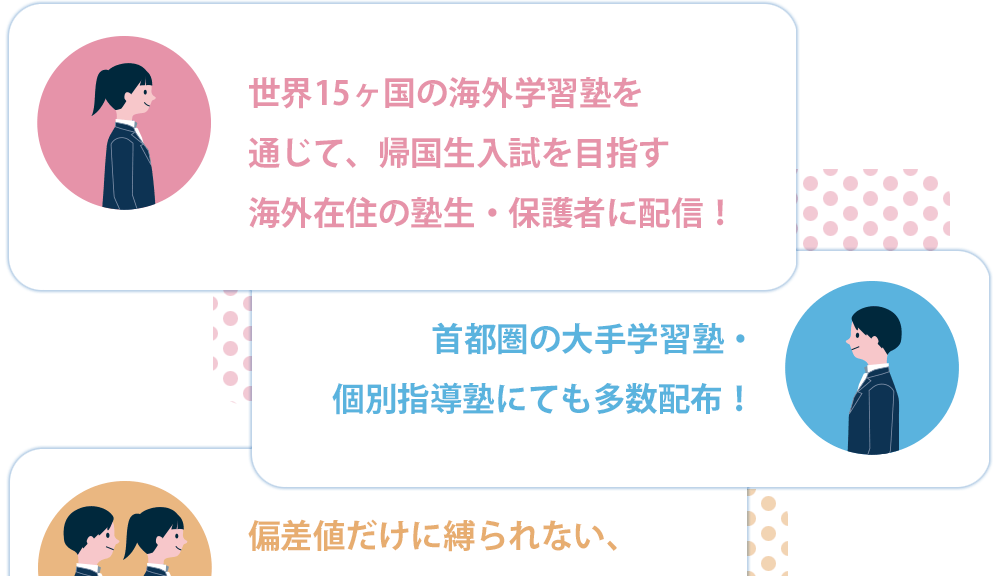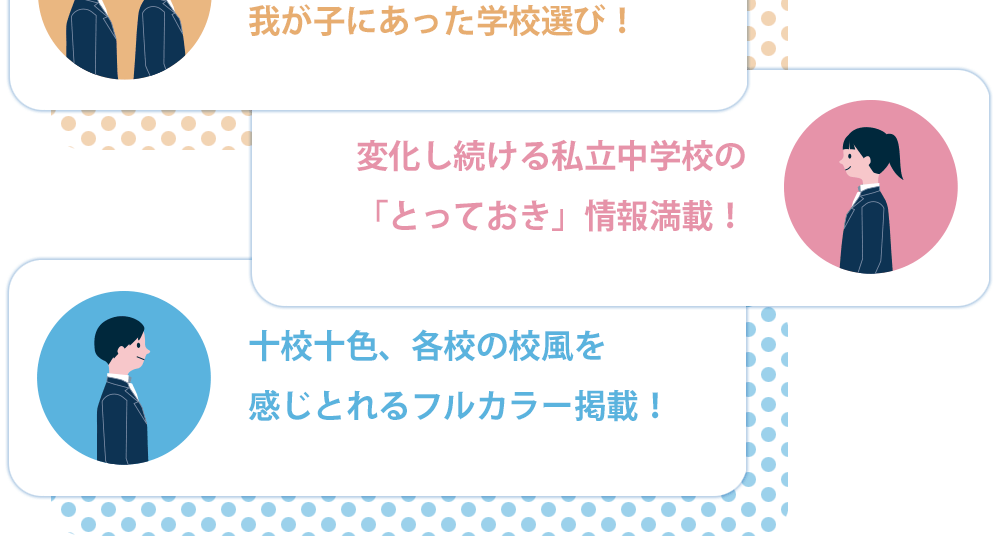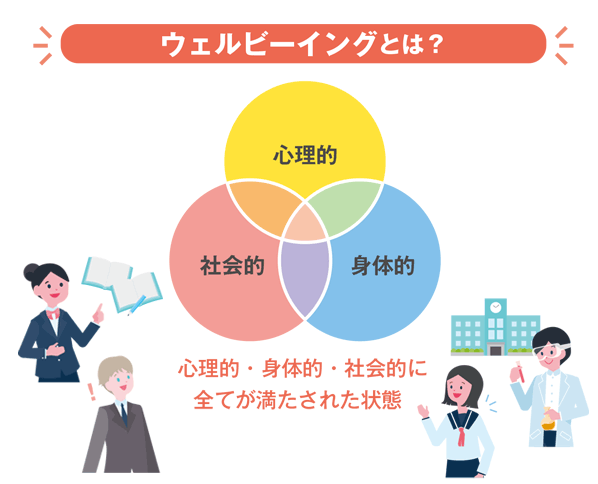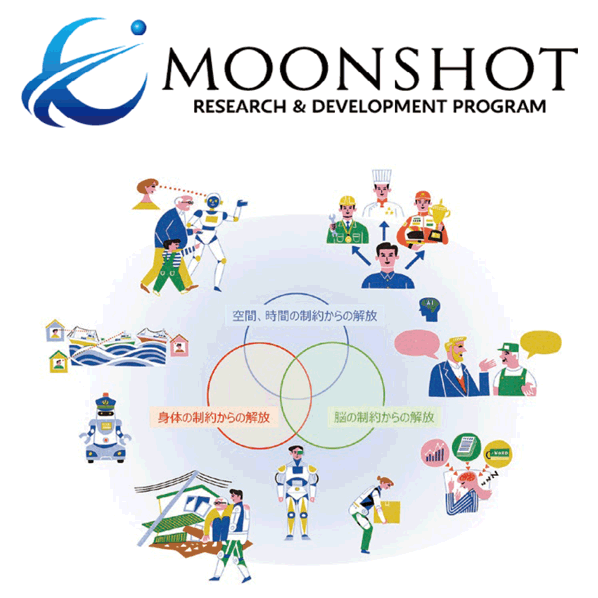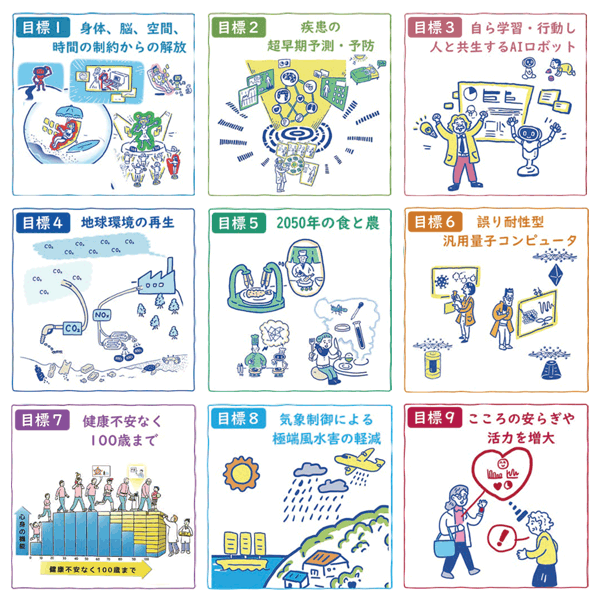SDGsからウェルビーイングへ!さらにムーンショット計画も視野に!
2020年初頭から世界の国々に大きな影響を与えてきたコロナ禍を契機に、世界中の学校や企業が、それまで以上に「SDGs」の解決課題を重視した活動を行うようになりました。それは日本の学校にも共通しています。そして、"Beyond GDP(GDPを超えて)"、「Well-being Goals(WBGs)」などといわれる次の時代に向けての課題が、すでに国連の活動や教育現場の課題として注目され始めています。
『SDGs』目標達成のためのキーワードが『ウェルビーイング』!
「SDGs」目標達成のためのキーワードの一つが“ウェルビーイング”と言われています。 国際連合広報センターのWebサイトでも、この2024年9月に開催される予定の一大イベント「国連未来サミット(Summit of the Future)」の目的や背景についての日本語版の資料も2023年10月に公開されています。
このサミットでは、国連が100周年を迎える2045年に向けて、世界が直面している重大な課題に対する協力の強化と、SDGsの次のグローバル・アジェンダを議論する予定で、ウェルビーイングが中心的な議題となる見通しが示されています。
たとえば、豊かさの指標としてのGDPには限界があるという考え方に沿って、"Beyond GDP(GDPを超えて)"をキーワードとして、人々のウェルビーイングに重点を置く経済システムの構築のために、いわば「Well-being Goal(s WBGs)」とも呼ぶべき枠組みの議論が始まるということで注目されています。この"Beyond GDP"で議論されている枠組みは、目指すべきアウトカム(=影響・結果・状態)の一つ目が「ウェルビーイングと主体性」であり、ウェルビーイングが他の「生命と地球の尊重(サステナビリティ)」「不平等の縮小と連帯の拡大(DE&I)」と 並んで、3本柱の一つとされていることに注目したいと思います。つまりは、今の小学生世代か゛社会の中軸を担う2030年代から2045年に向けての地球課題の一つが「ウェルビーイング」だということも意識して、わが子の教育環境を選んでいくことが必要となっているのです。
そして日本でも2050年に向けて「ムーンショット計画」が描かれた!
今の子どもたちが生きる2050年の社会を見据え、日本でも内閣府から2020年に「ムーンショット計画」が策定公開されています。ムーンショット計画の由来は、第35代アメリカ大統領 J.F. ケネディが月面着陸を成功させた「アポロ計画」にあります。この計画が人々に衝撃と感動を与えたことから、困難な目標を達成した結果、社会に多大な影響をもたらす計画を「ムーンショット計画」と呼ぶようになりました。この計画の目的は「人々の幸福を実現し、少子高齢化社会を克服して、誰もが夢を追求できる社会や高齢でも健康で人生を楽しめる社会の実現」です。さらに、サイバネティック・アバターの活用やAI技術を活かし、国際的なプラットフォームや新しい産業の創出、多様なライフスタイルの実現を目指しています。